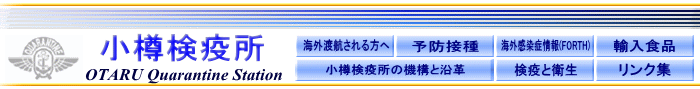 |
||||
| |
||||
|
|
||||
| 【輸入食品の安全を守るために】 | ||||
|
|
||||
| カロリーベースで約6割を海外からの輸入食品に依存している我が国において、輸入食品は国民の皆様の食生活の安定に大きな役割を担っており、その安全性の確保に向けた取組は益々、重要なものとなっています。 食品の安全性の確保に関して、我が国では、食品安全基本法及び食品衛生法が制定されています。厚生労働省では、国民の食の安全を確保するため、食品衛生法に基づき、毎年度、輸入食品監視指導計画(※)を定め、輸入食品等の安全性の確保に取り組んでいます。 小樽検疫所食品監視課では、監視指導計画に基づき、輸入者に対する監視指導や北海道内の港湾、空港に輸入される輸入食品等の監視及び検査を実施しています。 ※)監視指導計画の詳細は以下のリンク先「輸入食品監視指導計画」をご確認ください。 監視指導・統計情報(厚生労働省ホームページにリンク) |
||||
| 【検疫所による監視指導】 | ||||
 輸入食品の届出審査 |
 輸入食品の検査 |
 事前輸入相談 |
||
| 【輸入者の責務について】 | ||||
|
|
||||
| 輸入食品等の安全性の確保のためには、食品の生産から販売に至るまでの各段階において、食品等を輸入する食品等事業者(以下、「輸入者」といいます。)が自ら自覚と責任感を持って、安全な食品の供給に努めることが重要であり、その責務が食品衛生法及び食品安全基本法に規定されています。 | ||||
| 【食品衛生法第3条 食品等事業者の責務(要約)】 食品等事業者(食品の輸入においては輸入者)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物又は容器包装について自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 【食品安全基本法第8条(要約)】 輸入食品等の安全性の確保については、輸入者自らが第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する |
||||
| 参考)各法律の全文はこちら → 食品衛生法 食品安全基本法 |
||||
| 【輸入食品等の手続きについて】 | ||||
|
|
||||
| 海外から販売又は営業目的(有償、無償に関わらず、不特定または多数の者へ配布する場合を含む。)で食品等を輸入する者は、その安全性確保の観点から、厚生労働大臣に届出(食品等輸入届出)を行わなければならない旨が食品衛生法第27条において規定されています。 対象となる食品等とは、販売又は営業上使用する食品、添加物、飲食器具・容器包装及び乳幼児用おもちゃとなります。 小樽検疫所では、中国や米国をはじめとした国々から、畜産食品、農産加工品、魚介類や水産加工食品、飲食器具・容器包装を主とした様々な食品等が届出されており、検疫所の食品衛生監視員が届出に基づき、適法な食品等であるか審査、検査を実施しています。 |
||||
| 【食品衛生法第27条】 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
||||
| 【小樽検疫所に届出される食品の一例】 | ||||
 冷凍羊肉(畜産食品) |
 冷凍ゆでがに(水産加工食品) |
 冷凍スライスたまねぎ(農産食品) |
||
| 小樽検疫所 Copyright Otaru Quarantine Station's All rights reserved. |
||||