1.貨物の流れ
輸入される食品等の流れを簡単に示すと次のようになります。 |
 |
|
 |
| なお、検疫所への「食品等輸入届出」の流れは次のようになります。 |
 |
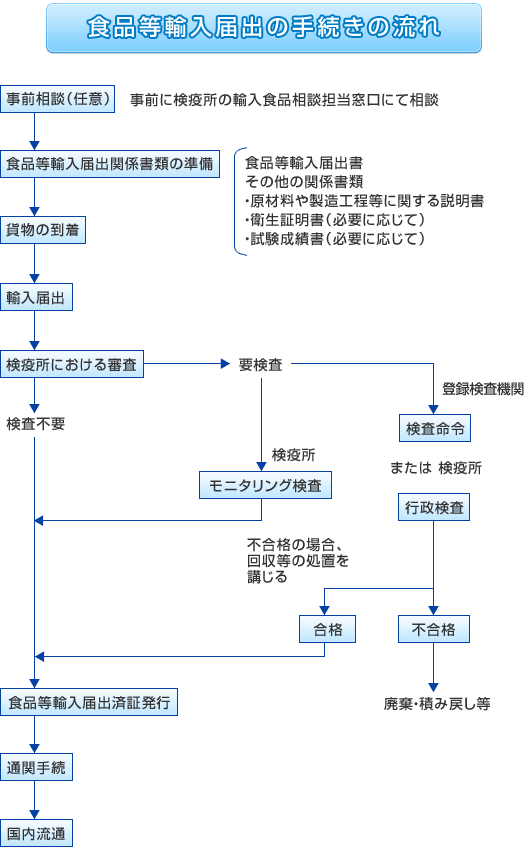 |
 |
2.食品等とは
食品衛生法の規定に基づき、食品等輸入届出が必要な「食品等」とは、以下のものをいいます。
①食品 ②添加物 ③器具 ④容器包装 ⑤おもちゃ(乳幼児を対象とするものに限る) |
 |
3.「食品等輸入届出書」 について
食品等を販売又は営業上使用する目的で輸入する場合、「食品等輸入届出書」を検疫所に提出することが必要になります。
(1) 届出場所
食品等輸入届出書は、輸入する貨物を保税状態で蔵置している場所(保税倉庫等)を管轄している検疫所の食品監視担当窓口(全国31カ所)へ提出することが必要です。
(2) 提出時期
食品等の輸入届出は、原則として、輸入する食品等が日本に到着し、保税倉庫に搬入され、食品衛生上の事故の有無を確認した後に提出することになります。 |
 |
4.手続き迅速化の措置
食品等の輸入手続きを迅速、且つ円滑に行うために次のような方法があります。
(1) 事前届出制度
すべての食品等について、貨物到着予定日の7日前から届出書を受け付けており、検査の必要な物等を除き貨物到着前又は搬入後速やかに届出済証が交付されます。
(2) 計画輸入制度
特定の食品等を繰返し輸入する場合、初回輸入時に輸入計画を提出し審査の結果問題がなければ、一定期間は次回からの輸入の都度の届出が省略できます。
(3) 外国公的検査機関の検査結果の受入
輸出国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、当該貨物について検疫所における当該検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。
(4) 同一食品等の継続的輸入
特定の食品等を繰返し輸入する場合、初回輸入時届出書に検査成績書を添付し、審査の結果問題がなければ、一定期間は当該項目について、次回からの輸入のつどの検査が省略されます。
(5) 輸入食品等事前確認制度
輸入される食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、当該食品等及びその製造加工業者を登録することにより、登録された食品等については、輸入時検査が一定期間省略(検査命令に係る検査及びモニタリング検査を行う食品等を除く)されるとともに、届出後速やかに届出済証が交付されます。
(6) 品目登録制度
継続的に輸入する食品等として、各検疫所窓口に必要書類を提出し、食品衛生法に適合する旨が確認されたものについて、届出書の記載事項の一部及び検査結果の登録が可能となる制度です。 |
 |
5.輸入前の調査
食品衛生法では、食品等事業者の責任において、食品等の安全性を確保するため、
①食品衛生に関する知識や技術の習得
②使用する原材料の安全性の確保
③自主検査の実施
④その他の必要な措置
を講ずるよう努めなければならないと規定されており、輸入食品等に関しては輸入者自らが食品衛生法に適合していることを含め、食品等の安全性を確認しなければなりません。
また、食品安全基本法においても、食品関連事業者の責務として、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講じる責務を有すると規定されています。
(1) 原材料、使用添加物、製造方法について
輸入する食品等の原材料(原材料の安全性確認)、使用添加物(原材料に使用している添加物も併せて)、製造方法について十分に調査することが必要となります。輸入に際しては、外国で違法に生産、製造加工された食品でないことを輸出国当局や輸出者、製造者に対して確認を行い、原材料、添加物、製造方法、検査結果が食品衛生法を遵守していることの再確認を行うよう求められています。また、輸入しようとしている食品等が、日本の食品衛生法に適合しているかどうか、輸入を決める前に確認しておくことが、輸入の際の経済的、時間的ロスを少なくすることにも役立ちます。 |
 |
| (安全性の確認のための資料) |
 |
| ・ |
輸出国、製造者及び製造所の名称と所在地、製品の名称(英名併記) |
| ・ |
製造者が作成・発行した社名入りの原材料表と製造工程表 |
| ※ |
原材料表は、使用した原料(食材)と添加物の具体的な化学名称を、全て記載したもの |
| ※ |
食品添加物の場合は、具体的な化学名称、基原、製法及び添加物製剤の場合は、添加物の含有率が確認できるもの |
| ※ |
器具・容器包装、おもちゃの場合は、材質、形状、色等が確認できるもの(カタログ等) |
| ※ |
製造工程表は、原料から製品に至る工程を図にしたもの |
| ・ |
上記の資料が英語以外の言語で記載されている場合は和訳したもの |
| ・ |
原料によっては薬事法に該当する成分か否かを薬事担当部署で確認し、その内容(確認日、確認先、対象物質とその取扱い等)を記録したもの |
|
| 日本に食経験のない食品等については、さらに詳細な資料の入手が必要となります。 |
 |
なお、検疫所では輸入食品相談指導室(全国13カ所:小樽、仙台、成田空港、東京、横浜、新潟、名古屋、大阪、関西空港、神戸、広島、福岡、那覇)を設け、担当官を配置しています。
輸入食品相談指導室では食品等の輸入者や関係事業者に、食品等の輸入手続き、検査命令制度や検査強化品目等の輸入時の検査体制、輸入食品等の安全性確保の取り組みに必要な日本の食品添加物や残留農薬等の規制、原材料の安全性確保に関する管理方法、食品衛生法違反事例等について情報提供や指導を行っています。
なお、来所相談は予約制の場合がありますので、各検疫所へ確認をして下さい。
(2) 自主検査について
自主検査については輸入する食品等の輸出国、原材料、使用添加物、過去の違反事例等を勘案し、現地における農薬等の管理、使用、検査等の管理内容に応じて必要な検査項目を設定します。
自主検査の実施は、食品等の安全性の確認の一つの方法であり、科学的な根拠となる検証の方法として有効な手段ですが、文書による確認の代わりになるものではありません。そのため、規格基準や添加物の適正使用等に関して、予め原材料表等の内容を確認して下さい。 |