 |
 |
飲食等に用いる器具や容器包装は、食品と接触し使用することから有害な重金属などの物質が食品を汚染しないように規格基準が定められています。陶磁器やガラス製品にあっては、色合いや輝きを増す技術としてカドミウムや鉛を含む原材料を用いることもあり、これらが基準値を超えて溶け出すことがないかを注意深く検査する必要があります。
食品衛生法で規制されるおもちゃとは「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃ」であり、食品、添加物、器具容器包装の規定を準用することと定められています。おもちゃの種類や原材料の違いにより定められている規格検査(重金属、鉛、カドミウム、ヒ素、亜鉛、フタル酸エステル類、過マンガン酸カリウム消費量など)の他、おもちゃの製造基準に定められた着色料の溶出検査を行っています。
|
|
 |
 |
 |
| 飲食器具等から溶出した試験溶液中の重金属を定量します。その際、ICP(誘導結合プラズマ発光分光分析装置)や原子吸光分光光度計を用います。いずれも微量の重金属を測定する分析装置です。 |
|
 |
|
 |
 |
  |
| サンプルから求めた表面積値より試験溶液を調製します。抽出後判定を行い、着色料の溶出が疑われる場合はさらに高速液体クロマトグラフにより定性試験を実施します。厚生労働大臣の指定するおもちゃについては、許可色素以外の着色料は使用してはならないこととされています。 |
|
 |
|
 |
 |
 |
| フタル酸エステル類は可塑剤の一種です。ポリ塩化ビニル樹脂を軟らかくしたり、加工しやすくするために繁用されますが、生殖毒性や発生毒性、催奇形性などが問題視されています。 DEHP(フタル酸ビス)とDINP(フタル酸ジイソノニル)の2つが規制対象で、おもちゃより抽出した、試験溶液をガスクロマトグラフ質量分析計にて測定します。 |
|
|
 |
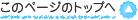 |